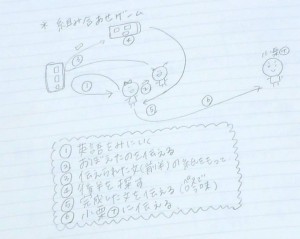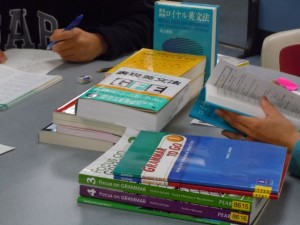Day 1復習
- self-study:p.10-14、p.16-17
Day 2 :本日の学習内容
- ノートとりの極意:自発的に!板書を写すだけのクセから抜けよう。(目標:秘書に採用されるようなノートづくりを!
- Summaryの悩み:何を書けばいいか、どうまとめたらいいか、何を主語にしたらいいか???
- 考えることを身につける:終点に早くつくことを求めるよりも、終点まで到達するプロセスが大事なトレーニング。
- おまけ:時事ニュース、特に新聞報道記事から「トピック」「メインアイディア」の取り方を学ぶ方法。
- p.23 Organizer,
- self-study:p.25〜29、p.34-35
長文の聞き方・読み方:つかんだら離さない
- 各パラグラフのトピックをつかむ。
- Main ideaとsupporting detailsを分類する。
- タイトルを忘れない!
- Predictionを欠かさない。次へ次へと推測をしながら、確認していく。(憶測、思い込み禁止!)
- andは時には「等位」ではない。→”Changing Lifestyles and New Eating Habits”の”and”は、因果関係を示す役目。ただの「と」ではない。
サマリーの書き方
- 日本語アタマの悪いクセ(主語がやたらに長い等)から脱却しよう。
- だらだら語彙を並べて長くしているのに、情報が不足している・・という愚文にならないようにしよう。
- detailsに踏み込まないようにしよう。(もっと内容まで踏み込んで、が求められる場合を除く)
- 動詞に行き詰まったら、主語の視点を変えて推敲する。
- 重複する情報、余分ないいまわし(redundancy)は消す。→コンサイスに最大限に伝える!
- 重複する語彙表現を改良できるだけ、改良する。(時には断念もしかたがない)
- 上級者は、幾通りもの表現を考えられるようにする。
本日のアクティビティ:聞けるようになるために読むペアレッスン[1]
- 5段落の中にあるセンテンスがバラバラのカード(26枚)に。(抜粋センテンスは本文のまま)
- ペアで、内容にそってカードを分類。
- 分類されたカードを、マクロ情報(topic sentenceやmain ideaかも)、ミクロ情報(supporting details)、ミクロの中のさらにミクロ・・と分類
- ヒント1: 最初の文のみのヒント→5つの段落展開を確認
- ヒント2: 音声を聞く→音声情報をヒントにカードを並べ替える→さらに情報の階層関係を確認
- 本文を見て確認
本日の教訓:聞き流さない
教材の質がよい場合、言葉や情報順序が推敲、吟味されています。それを使って聞く、読むトレーニングをする際、それぞれの力をつけるだけでなく、語彙表現の使われ方、情報序列のしかたを学ぶことができます。よいインプットはよいアウトプットにつながります。文法もそこに詰め込まれていることもお忘れなく。
参考
Learning to take notes(小栗ブログ2013年9月30日より)