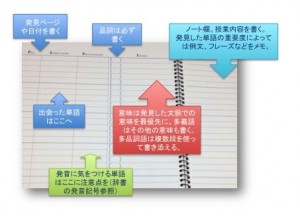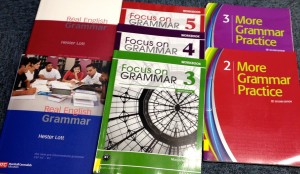「英語を身につけたい」と思うなら
by小栗成子
2012年12月18日
「英語を身につけるのに、効果的な方法はなんですか?」とよく問われます。「この方法は、効果的ですか?」とも。 たしかに効果的な学習だと思える方法はいくらでもあります。でも、それを「効果的に」学習できるかどうかは、自分次第だということをまず忘れないでほしいです。
残念ながら、学習の成果は、一日、一週間、一ヶ月、一年程度で現れるとは限りません。早い人もいますし、遅い人もいます。 「目安」は最低でも3ヶ月単位、とよくお話しています。それゆえとてつもなく根気がいります。そして、時間がかかります。自主学習記録に「時間がかかって前に進まない」と書かれていることがあります。身に付いていないのに、時間をかけずに、前へ前へと進む・・・ではまずいですよね。
残念ながら、「根気」x「時間」=「ことば力」というような、簡単なものでもありません。ことばは、糸を紡いで、織りあげていくようなもの。たくさんのことをして、糸を何万本も、ただ並べて置いていっている人をみかけます。あるいは小さな布を織って、それを壁にはりつけているだけのような人もみかけます。織り込んでいかなくちゃ。あるいは、パッチワークのごとく縫い合わせていかなくちゃ。そうしないと、1つの「ことば」にならない。
ヒント1:長い道のりを、一歩一歩じっくり進むほうがいい。
毎回の学習、数分、数時間で、何がどうしたとミクロにならないこと。学習はもしかすると永遠に続くもの。そのプロセスを楽しむことで、土台を作っていこうとしてはどうでしょう。グローバルすぎて、おおざっぱな人もいますが、「これでいいのか」「これで効果があるのか」と毎回、毎回、ミクロにつま先だけをみていても苦しいだけ。楽しく歩いて、時々振り返って、足跡をみながら反省する。その反省から次を考える、というのはどうでしょう。その前に、「効果をあげる」ってどんな効果?目標は「効果的な学習の達成」なの?道草も含めて、自分の「道」。教材でいうと、シリーズもののレベルをどんどん上げていくのは、危険なこともあります。時として、レベルはあげず、同レベルの別のものに取り組んだほうが力がつくことがあります。レベル(数字ね)があがると、それだけで満足してしまう人もいます。
ヒント2:目標は混線しないほうがいい。
◯◯のスコアを上げたいし、できれば(ついでに)英語が「使えるようになりたい」。目標を混線させると、自分の首がしまることになりかねません。それじゃ、楽しめないよね。やっぱり、欲張りすぎても、二兎追う者は一兎も得られない。試験対策の中に、「使えるようになる」要素が入っていることは確か。「使えること」を試されているのが試験なのだから。でも、試験対策だけをしているとどうなるか・・・。「英語」のうちの、わずか一部しか触れていないことに(本当は)なっていることに、気づいておきましょう。その上で、「どのくらいの(点数や級をとるだけの)力があるか」を自分にも人にも示すために、「資格」試験はあるのだと思うけどな。「目安」にはなるけど、「実力」はそれだけでは測れなくはないのかな。
ヒント3:得点より「楽しい」を追求したほうがいい。
学んでいることを忘れるほど、楽しめてしまうこと・・経験したことはないかな?「え?今日、もう終わり?」というような授業を受けたことはない?「楽しい」という基準は人それぞれだけど、「学習している自分」が好きなままだったら、結構危険かもしれない。「なるほど!」「そうか!」というような発見や、「わかった!」という感動を得たことはあるかな。それとも発見も感動もすべて、点数化しているのかな?そんなに点数付けして、楽しいのかな。
ヒント4:土台はしっかりしていればしているほどいい。
自主学習カウンセリングでも、授業でも必ずといってよいほど触れるていると思いますが、土台はどうなっているのでしょう。母語なら毎日使える環境にあるのですから、それを怠らないことが、母語も、そして続いて英語も磨くことにつながると思ってみてはどうでしょう。
母語を使わず、母語の運用能力を高めることを怠っていて、「英語を身につけたい」という人は多いです。どちらも離ればなれのものではありません。母語だと「これは手強い」と高望みをしないのに、英語の教本だと自分の力よりも、遥かに高いレベルのものを使おうとする人がいます。英語の教本だと、見た目で馬鹿にする人がいます。「辞書を引かずに読めるもの」なら聞く事。読めるし、聞けるものであれば、口に出してみる事。語彙は基礎から、文法も例文が「読める」レベルのもので、きちんと固めていきましょう。
英字新聞を読めるようになりたければ、日本語の新聞の速読を。話力を高めたければ、母語での話力を高める努力を怠らないこと。このごろは、母語が2つ、もしくは半分ずつ、という人たちもいます。その場合は、どの言語か1つを土台にできるまで固めながら、英語も学ぶことをおすすめします。
ヒント5:「適当」ではなく「適度」のほうがいい。
きわめて適当な動機で学習をし始める人がいます。もちろんそれもいいです。が、ずっと「適当」にはしていられないことを覚悟して下さい。「だいたい通じればいいんです」「だいたい読めればいいんです」そんな「だいたい」や適当ならば、自分のためだけに使うものと覚悟して下さい。世の中では通用しないし、ましてや仕事では「適当」は困ります。適当なまとめが返ってくる人に、仕事を頼むわけにはいかないからです。
適当な語彙、適当な文法、適当な発音・・・の人に仕事は頼めません。 英語をどんな風に、どこで使うか・・・によって、「適度」さは異なります。その「適度」さを目指してください。
プロならプロをめざす。趣味なら趣味でいい。神経質すぎる人は、自分を緩めて。緩みっぱなしの人は、自分を引き締めましょう。頭の堅い人は、柔らかくする方法を、頭が緩すぎるひとは、少々しっかりと、自分の「適度」を探しながら、学習してみるのはどうでしょう。