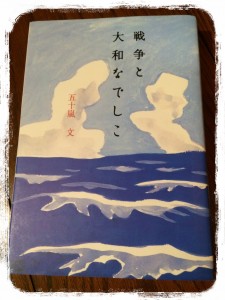学習ポイント
復習:Day 2/ペアアクティビティ:カードシャッフル→段落構成→各段落トピックの書き方より
英語を書くときの注意
- 語彙をむやみに、推敲なく並べない。(長ければよいってわけはない!長くて何も述べていない、メッセージが伝わらない文は愚文)
- 日本語の「〜で」「〜ので」「〜から」に注意:日本語ではだらだら連なる文も、英語では1文ずつ区切ったほうが効果的であることが多い。特に、書く初心者は、コンサイスにまとまった文を書く、簡潔に伝える方法を身につけて、次により一層よい表現方法を身につけていこう。
- 日本語あたまで、名詞句(主語)をなが〜〜〜〜〜くしない。節の順序も、効果的なほうをとる。→何が一番述べたい事か、が基準!
- よいインプット(読み)を重ねて、よい書き方ができる人になろう
- たった1つの語彙が、余分だったり、内容を的確に伝えられたりする。例:increasing。”Americans’ nutrition awareness”といったときと、”increasing ….awareness”といったときの違いは大きすぎるほど、大きい。
- 副詞は決意して使う:副詞ほど余分につけると、大幅に意図とずれ、意味がぼけてしまうものはない。慎重に、的確に副詞を使えるようになろう!
- サマリーを書くときのポイント:(1)情報の順序、(2)情報の連結、(3)主語選択、(4)動詞選択、(5)その他の要素の添加
テキスト使用上の注意
音声とともに、テキストで本文確認。語彙表現も確認。情報序列、順序にも注意。
テキスト本体に書き込みをたくさんして、自分のノート化とする使い方もあり。本文部分に書き込みをするのがいやな場合は、コピーした本文に書き込みをする方法もあり。何も記入しないでいては、学んだことを振り返ることはできない!!(なんてもったいないこと)情報と情報の関連をしっかりと読み取る訓練を!
辞書を使う意味
たとえば、「決める」という日本語を英語にすると?和英辞書を引いてみるといくつかの候補があがってくる。
- decide
- determine
- choose
この候補たちにすぐに飛びついてはいけない。各候補のニュアンス、適切な使用場面を確かめるために、例文をよく見てみる必要がある。「もしかして、この場合はdetermineかな?」と思ってもまだ「?」なところがあるのなら、「英和」で確認。例文をしっかりみて、自分が伝えたいことと類似した場面で使われていれば、その語彙が使える・・ということ。
★「この日本語で伝えようとしていることの意味は、英語でいうとどれに当てはまるか」を考えるのを忘れない!
テキストの英語表現から
- At the same time:ここでは、同時期を表しているのではなく「AだといっているのにBも同時に」という逆説のニュアンス。
- The way people live determines the way they eat: “determine”であって、decideでもなく、ほかでもない。determineが的確に使われている例。「AによってBが決まる。「[BはA次第」「〜によって変わる」というニュアンスを伝えている例。
- Awareness of ... leads them to consume...:"lead"で因果関係を的確に伝えている例。こういうleadが使えるようになりたい。
本日のリスニング:Note-takingにチャレンジ
Chapter 4 Language: Is it Always Spoken?
- 6段落のパッセージを、タイトルから内容推測をした上で、各段落のトピックを追いながら聞く(p.59:リスニング中は参照不可)
- パラグラフ内のマクロな情報をまずノート。(キーワードを逃さないぞ、という意気込み!!)
- Information Organizationをヒントにノート。
- 繰り返し聞く間に、マクロ、ミクロの要点をノート。
- 逃さない意識:数値、数字、固有名詞(が表していることがら)、否定語、最上級、比較。
- この文の内容は、2者の類似点、相違点を明示していることに焦点をあてながら、ノート。
★「音」を聞くのではなく、「内容」を聞く!!
Day 3/ペアアクティビティ:カードシャッフル→段落構成
- 5段落の中にあるセンテンスがバラバラのカード(26枚)に。(抜粋センテンスは本文の内容を少々簡潔に書き換えたもの)
- ペアで、内容にそってカードを分類。
- 分類されたカードを、マクロ情報(topic sentenceやmain ideaかも)、ミクロ情報(supporting details)、ミクロの中のさらにミクロ・・と分類
- ヒント1: 最初の文のみのヒント→5つの段落展開を確認
- ヒント2: 音声を聞く→音声情報をヒントにカードを並べ替える→さらに情報の階層関係を確認
[アクティビティのポイント]
音声ヒントをもとに、思考する。そのプロセスが「耳で読む」力を育てます。
ノートテイキングする際には、ここで学んだマクロ、ミクロの分類を活かせるようになることを目標にトレーニングします。
※時間終了後もまだ残って、ペアで最善策をとろうと検討していた姿が素敵でした。終了後は講師がテーブルに分類されたカードをホワイトボードへ貼付け。その際、マクロ、ミクロが判読できるように必要な部分をインデントして、カードを貼付けました。
Self-study:p.61, p.62-64, p.64-65, p.66-p.71